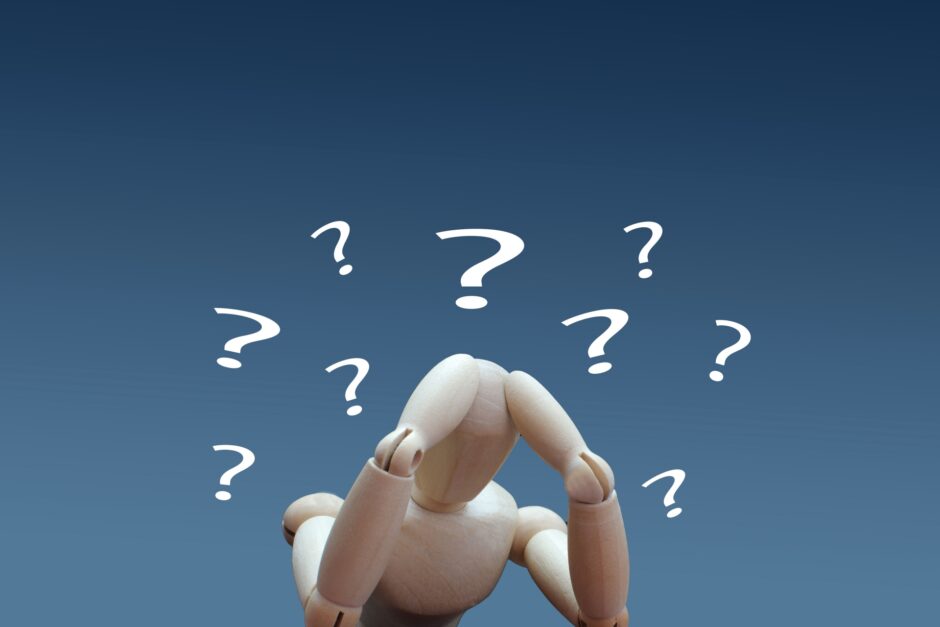こんにちは、大久保です。
新学期が始まってしばらく経ち、新生活に慣れてきた頃合いかと思います。
それと同時に、スタート時の緊張が緩んで中弛みが起きやすい時期でもあります。
この時期に気をつけたいのが、「燃え尽き症候群」です。
皆さんは大きな目標を達成した後に「次に何を頑張ればいいのかわからない」「やる気が出ない」と感じたことはありませんか?それが「燃え尽き症候群」です。
長期間努力を続けた後に、その努力の理由がなくなり、モチベーションが急激に低下してしまう状態のことで、例えば、受験勉強を頑張って第一志望校に合格したのに、入学後に勉強へのやる気を失ってしまう、というのがよく言われる燃え尽き症候群です。
また、入試などの大きなものだけでなく、部活や習い事の大会、学校の試験や検定が終わった後に、何も手につかなくなってしまうこともあります。
これは誰にでも起こりうる現象であり、決して特別なことではありません。
燃え尽き症候群を防ぐには、新たな目標を見つけることが大切です。
そこでおすすめなのが、「10年後の自分を想像すること」です。
10年後、自分はどんな仕事をしているのか、どんな暮らしをしているのか、どんな人たちと関わっているのかを具体的に考えてみましょう。
その理想の未来から逆算すると、今やるべきことが自然と見えてきます。
例えば、「将来は医療関係の仕事がしたい」と思うなら、そのために入りたい大学や専門学校はどんなところか、そしてその学校に入るためにどんな科目が必要なのか、といった具合に、いまの自分が取り組めそうな目標に落とし込んでいくのです。
とはいえ、目標を決めるというのは実は簡単なことではありません。
目標が決まったとしても、「どこから手をつけたらいいのかわからない」と感じることもあるでしょう。
そんなときは、目標を細かく分けて、より小さなステップから始めるのがコツです。
これは社会人がビジネスの世界でも言われるコツで、スモールステップと呼ばれることもあります。
例えば、「英語ができるようになりたい」と思って目標を「英検2級を取る」としても、そこからさらにスモールステップ化しなければスタートが切れません。
例えば、「本屋さんに行って対策教材を1冊買ってくる」「毎日10個の英単語を覚える」といった、小さな一歩から始めてみてください。
実際に行動を始めてみることで、次に必要な行動や方向性がわかるようになってくるものです。
スモールステップを積み重ねることで、無理なく次の目標へと進んでいくことができます。
燃え尽き症候群は誰にでも起こりうるものなので、自分がそうなっているとしても自分を責める必要はありません。
ですが、みなさんが人生で本当に叶えたい夢や目標を達成させるためには、なるべく早く燃え尽き症候群から脱却することが大切です。
一つの目標が終わったら、それは新たなスタート地点でもあります。
常に成長し続けるために、新たな目標を見つけ、一歩ずつ前進していきましょう。
もし、目標の立て方がわからなかったり、なにから取り組めばいいかわからない、という悩みがあれば、いつでも匠の先生に相談してくださいね。